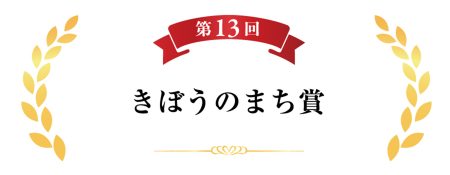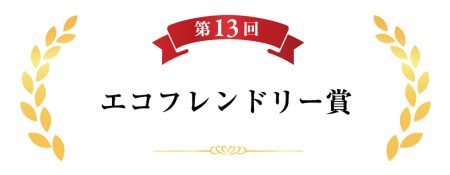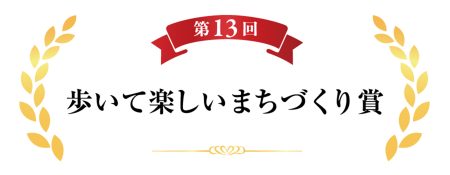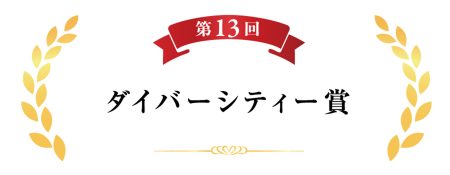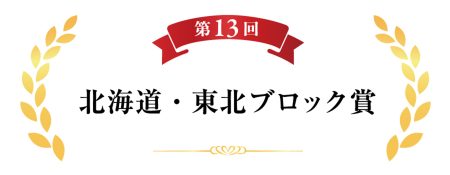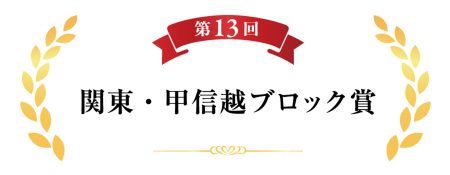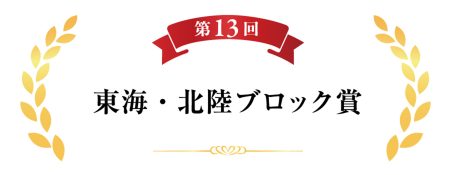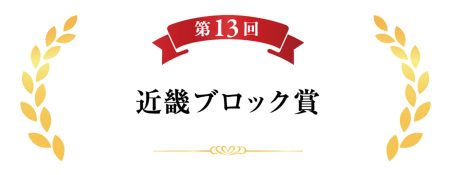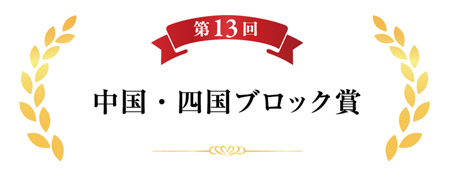ごあいさつ
全国各地の新聞46紙と共同通信社が主催する地域再生大賞は、13回目を迎えた今回、「創ろう新時代 希望掲げて」をサブテーマに、ポストコロナを見据えた取り組み、新しい担い手の活躍、地域からの発信力に着目しました。
農福連携のパイオニア、格差のない読書環境づくり、漂着ごみを起点にした環境保護活動-。人と人、人と地域の関わりを見つめ直す機会ともなったコロナの時代を経て、大賞、準大賞をはじめ各賞からは、支え合って共に生きていく意欲と力が地域にしっかり根付いていること、そして視野を広げながら未来に向けて膨らんでいることがうかがえました。ともすれば顔を下げがちな厳しい時代に、各団体の存在と活動は大きな希望です。
今回を含めて延べ650団体に及ぶ受賞団体の活動をまとめた「まちづくりチャレンジ650」は3月、ウェブ公開します。地域をもり立て、そこで生きる喜びへのヒントを得て、それぞれの活動がさらに熱気のこもったものになることを願ってやみません。
第13回地域再生大賞実行委員会
委員長 小市 昭夫
(信濃毎日新聞社 取締役編集局長)
【選考委員紹介】
第13回地域再生大賞の選考委員は次の皆さん。

沼尾 波子さん(ぬまお・なみこ)=委員長 慶応大大学院修了。2017年から東洋大教授。地方財政が専門で地域づくりを支える行財政システムを研究

大桃 美代子さん(おおもも・みよこ)タレント。新潟県中越地震で実家が被災したのを契機に食育や農業、地域振興に取り組む。新潟食料農業大客員教授

佐藤 宏亮さん(さとう・ひろすけ)早稲田大大学院修了。18年から芝浦工業大教授。建築の視点から各地のまちづくりに参画している。愛知県出身

藤波 匠さん(ふじなみ・たくみ)東京農工大大学院修了。15年から日本総合研究所上席主任研究員。地域再生、人口問題などが専門。神奈川県出身
【選考委員長講評】
営みを次世代につなぐ
沼尾波子選考委員長(東洋大教授)
「創ろう新時代、希望掲げて」をうたった今回、さまざまな地域課題にチャレンジする優れた取り組みが多数寄せられた。活動実績が3年に満たない団体が比較的多かったが、実績は未知数でも、アイデアや手法、戦略には目をみはる活動が多かった。 空き家活用、多文化共生、自然環境の保全再生、子ども・子育て支援など、地域課題が多様化・複雑化するなかで、活動の専門性も高くなっている。また、美しいデザインや、機能性を追求した地域資源の活用、文化の発信を行う事例も多く、印象に残った。地域の暮らしを楽しみ、その営みを次の世代につなごうという希望を掲げた活動には元気づけられた。 大賞「花の木農場」は農福連携のパイオニア。障がい者の就労と社会参加に向けて50年近く事業を展開してきた。最近では、地域内外の担い手との連携・交流を通じた新たな社会参加と地域振興にも挑戦する。 準大賞「北海道ブックシェアリング」は、書物や絵本を媒介に人と人とをつなぎ、学校図書館への支援にも取り組む。「対馬CAPPA」は、海外からの漂着ごみというグローバルな課題に地域で立ち向かう。
メッセージmessage


第13回ノミネート団体のページで
活動の詳細を紹介しています
北海道・東北


室蘭イタンキ浜鳴り砂を守る会
(北海道室蘭市)
海岸の環境を守る人育成へ、出前講座や漂着物展示


はちのへ未来ネット
(青森県八戸市)
子どもと親世代が集い、話し合い、悩みを共有できる場


NEXT REVOLUTION
(岩手県八幡平市)
起業家養成のプログラミング合宿、移住のきっかけに


六日町合同会社
(宮城県栗原市)
空き店舗改修し移住者に提供、商店街に希望生む


湯50(ゆ ごじゅう)
(山形市)
蔵王温泉の若手経営者らが空き物件をカフェとバルに


なみえアートプロジェクト「なみえの記憶・なみえの未来」
(福島県南相馬市)
知的障害のある作家が住民の思いを屋外アートで表現
関東・甲信越


ダイバーステイ
(栃木県小山市)
条件の悪い空き家を生かした農村民泊に多くの若者


前橋工科大 堤洋樹研究室
(前橋市)
公営団地にシェアハウス、学生が住んで課題解決


暮らしの編集室
(埼玉県北本市)
団地の空き店舗がジャズ喫茶と工房に、住民の居場所


NIPPONIA SAWARA
(千葉県香取市)
北総の小江戸で古民家を宿泊施設やレストランに


東京スリバチ学会
(東京都江東区)
凹凸地形の街を歩いて魅力発掘、全国に連携拡大


EDGE
(山梨県小菅村)
古民家を再生、特産食材使い村を「丸ごとホテル」に


つくえラボ
(長野県富士見町)
高齢者が移住者に農業技術伝授、アートプロジェクトも
東海・北陸


善商
(富山県入善町)
商工会の有志が設立し特産品開発、高校生も巻き込む


当目
(石川県能登町)
棚田米を商品化し伝統食復活、学生の合宿受け入れ


加子母木匠塾実行委員会
(岐阜県中津川市)
大学生が木造建築を実践的に学ぶ合宿は約30年に


シズオカノーボーダーズ
(静岡市)
障害者、健常者が一緒にダンスやパフォーマンス


尾州のカレント
(愛知県一宮市)
日本一の毛織物産地の魅力を若手社員が発信


むすび目Co-working
(三重県南伊勢町)
共働スペースやシェアキッチンで人をつなぎ、移住支援
近畿


木津川アート
(京都府木津川市)
木造公民館や米蔵、畑がアート作家の展示会場に


草むらの學校
(兵庫県丹波篠山市)
森や山で遊び、学びながら、これからの衣食住を探求


奈良新しい学び旅推進協議会
(奈良市)
歴史や文化が教材、修学旅行生らに深い学びを提供


和歌祭保存会
(和歌山市)
徳川家ゆかりの伝統行事存続、失われた芸能を復活
中国・四国


未来
(鳥取県倉吉市)
ウオーキング大会に国際交流、次世代の郷土愛育む


江の川鉄道
(島根県邑南町)
廃線の駅舎や線路を生かしトロッコ運行、観光客呼ぶ


基町プロジェクト
(広島市)
復興支えた公営アパート群、アート核に記憶伝え残す


3in(サンイン)
(山口県長門市)
高校生が持続可能な最新の魚養殖や販売に挑戦


徳島文学協会
(徳島県神山町)
地方でハイレベルな文芸誌、受賞作家相次ぎ誕生


天体望遠鏡博物館
(香川県さぬき市)
廃校を活用、望遠鏡の寄贈を受け修復して展示


今治コミュニティ放送
(愛媛県今治市)
市民パーソナリティーが地域に根差した番組づくり


こうち絆ファーム TEAMあき
(高知県安芸市)
障害者やひきこもりの人の就農を支援、林業とも連携
九州・沖縄


子どもパートナーズHUGっこ
(福岡県古賀市)
子育てを支援、小中高生の居場所をつくり夕食提供


灯す屋
(佐賀県有田町)
歴史的町並みで空き店舗活用のイベントや移住支援


坂本町災害支援チームドラゴントレイル
(熊本県八代市)
山道を走る愛好家らが災害復旧やシカの食害対策


日田もりあ下駄い
(大分県日田市)
多世代のメンバーが特産のげたでダンス、地域を発信


満月食堂
(宮崎県延岡市)
離島のにぎわい復活へ、地元の魚提供、加工食品も


ハッピーモア
(沖縄県宜野湾市)
小規模農家が育てた野菜を直売、出荷量を増やす


中城村南上原組踊保存会
(沖縄県中城村)
創作組踊で新興住宅地の子どもを健全に育てる